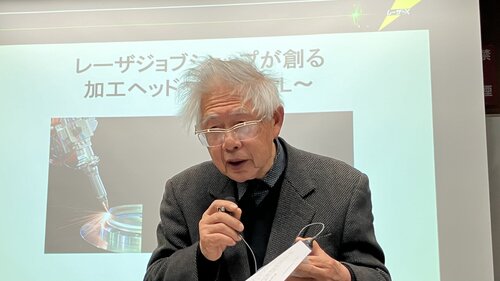中部レーザ応用技術研究会 第120回研究会「レーザ加工を支える周辺機器(加工ヘッド編)」を開催
1980年代から溶接工学に精通し、当時はまだ認知度がほとんどなかったレーザ加工技術の研究を牽引してきた沓名宗春先生。
今回のWelding Mateでは、そんな沓名先生が率いるレーザ企業・団体の集合体、中部レーザ応用技術研究会が2月19日に開催した「第120回レーザ研究会」について紹介する。
このレーザ研究会は、毎回、異なるテーマを設定して開催されているもので、今回のテーマは「レーザ加工を支える周辺機器(加工ヘッド編)」だ。
■開会挨拶:沓名会長
■レーザジョブショップが創る加工ヘッド「OPTICEL」:レーザックス周辺機器事業部長、鈴木裕之氏
■最新のロボット切断技術:エル・ビー・ウェルド、松岡信氏
■進化を続けるガルバノスキャナ・レーザ加工をサポートする機能:コヒレント・ジャパンマネージャ、杉澤光彦氏
■Fast compact scanners for e-mobility applications with a focus on welding contacts for cylindrical batteries:スキャンソニックセールスチーフ アクセル・ルフト氏
■閉会挨拶:武田晋副会長
今回の講演でキーポイントとなった一つが、「多くの発振器メーカーが加工ヘッドを製造する中、加工ヘッドメーカーの役割とは何なのか」だ。これに対して、各社が講演の後、回答を行った。
レーザックスの鈴木氏は、加工ヘッドメーカーの役割について「レーザ加工機メーカーが自社で加工ヘッドを製造する場合と異なり、加工ヘッドメーカーは豊富なラインナップを持つ。つまり、クライアントの要望に応じた最適なモデルを提供できるカスタマイズ性こそが、加工ヘッドメーカーの強みだ」と話した。
エル・ビー・ウエルドの松岡氏は、「当社では米国企業製の加工ヘッドを多用し、それをシステム化して提供している。レーザ加工機と比べると、加工ヘッドに関する情報は手に入りにくい。しかし、米国市場では日本にはない軍事産業向けの技術開発が進んでおり、これまでの事例と豊富な経験を活かして、日本のレーザ加工機メーカーやシステムエンジニアに最新情報を提供できる点が強みだ」と述べた。
コヒレント・ジャパンの杉澤氏は、「コヒレントはM&A(企業買収)によって、レーザ加工機と加工ヘッドの両方を製造する能力を獲得している。その理由は、加工ヘッド専門メーカーの持つ市場に適した高性能な技術を、いち早く製品化するためだ。加工ヘッドの開発は、その分野を深く掘り下げることでしか、レーザ加工機の能力を最大限に引き出すモデルを作ることができないほど奥が深い」と説明した。
スキャンソニックのアクセル氏は、「当社は加工ヘッドメーカーでありながら、複数のレーザ加工機メーカーをM&Aしている。加工ヘッドメーカーとレーザ加工機メーカーの両方の視点を持つことで、より迅速に顧客の要望に応えることができると判断した」と述べた。
レーザ技術は、現在も日進月歩で進化を続けている。一般的には、レーザ加工機メーカーが自社でカスタマイズした加工ヘッドの方が最適と考えられがちだが、加工ヘッド専門メーカーには特定分野に特化した高度な専門性があることが、今回の講演を通じて明らかになった。また、迅速に市場のニーズへ適応するためには、そうした専門性が不可欠であることも、多くの講演者の発言からうかがえた。




 SNSシェア
SNSシェア